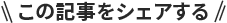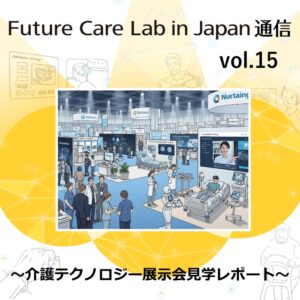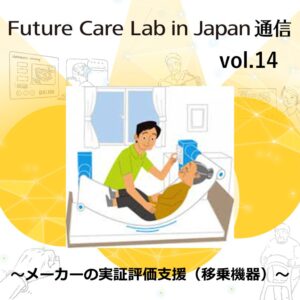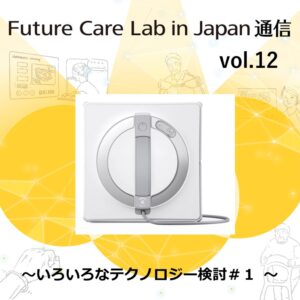Future Care Lab in Japan通信 Vol.12
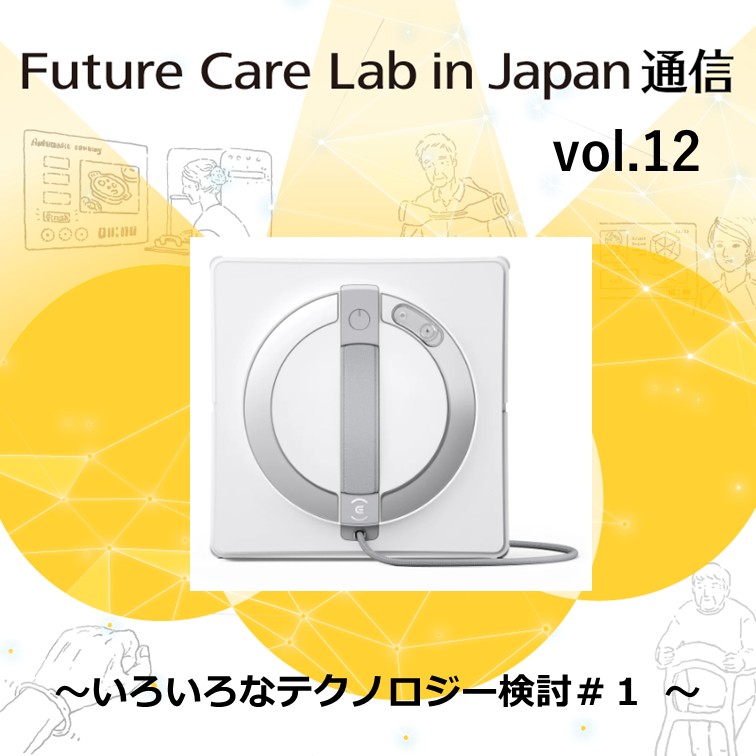
この連載ではFuture Care Lab in Japan(以下FCL)という研究所について、何を目指し、どんなことをしているのかをご紹介していきます。
第12回目は『いろいろなテック検討』
介護現場には、それぞれの環境によるニーズや課題が溢れているため、現場の責任部門から「特定のテクノロジーについて使えるものなのか確認してほしい」という依頼が寄せられます。
今回はその中のひとつ「窓ふきロボット」について、精度・安全性に問題がないか、また運用する上で課題がないかなど、検証した結果を共有します。
― 現場の課題 ―
介護施設の清潔な環境は、ご利用者さま の快適な生活を支えるうえで大切な要素です。最近では、床清掃ロボットなどが導入されている施設もあります。見落としがちなのが窓清掃で、窓ふきなどの清掃業務は時間と労力を要し、スタッフの負担になることもあります。実際に、200床の大規模施設では、窓清掃が行き届かず困っていました。そこで、「テクノロジーの力で何とか解決したい」という現場責任部門からの依頼を受け、「窓ふきロボット」についてのリサーチから実証までを行いました。
― 窓ふきロボットとは? ―
窓ふきロボットは、自動で窓ガラスを掃除し、人の手による作業を軽減することを目指したテクノロジーです。吸引力を利用して窓ふきロボットがガラスに張り付き、ガラス面を移動しながらまんべんなく拭き上げることができます。吸引タイプ以外にも、かつては磁力でガラス面の表裏を挟み清掃するロボットがありました。しかし、今は生産が終了しており、現在市販されているものは吸引タイプのみになっています。

実証で使用した窓ふきロボット(Ecovacs WINBOT W2 OMNI)
― 実証を経て分かったこと ―
FCLにある模擬環境で、水垢がついた窓ガラスと砂埃がついた窓ガラスを再現して、実証を行ってみました。

FCL実証の様子
窓ふきロボットは、吸引力により張り付くため、それなりの騒音がします。当初は掃除機と同じくらいの騒音を想定していましたが、実際はそれより少ない騒音レベルだったため、日中に使う分には問題なさそうです。
また、窓ふきロボットが落下しないかについては、運転中に故意に強い力で引っ張らない限り、ガラス面から外れることはありませんでした。
肝心の清掃能力については、比較的汚れが少なければ1度の拭き上げできれいにすることができました。しかし、頑固な汚れ、特に外側の砂埃がついたガラス面の場合には、何回か回数を重ねないと汚れが落ちませんでした。
そして、窓ふきロボットを使用する上で、避けて通れないのが、次の窓への移動に人手が必要であるということです。窓ふきロボットは、自動でサッシを跨ぐことができません。そのため、自動清掃が終わるたびに人がロボットを次の窓へ移動させる必要があります。
何社かのメーカーや清掃業者に相談しましたが、残念ながらこの点は現状のテクノロジーでは解決できないとのことでした。
— 最後に ―
世の中にはさまざまなテクノロジーがありますが、それぞれのテクノロジーが現場でそのまま手放しに使えることは稀です。
今回の実証で、窓ふきロボットの課題が分かりましたが、そのような現状を踏まえたうえで、現場で使うにはどのような工夫が必要になるのかを考えることも重要です。これからもFCLで継続的にリサーチを続けていきます。
私たちのFCLでは、引き続き介護現場のニーズに応じて、介護される人・する人の仕事を含めた生活をより良くし、活用し続けられるテクノロジーを追求していきます。これからも皆さんの声を聞かせてください。一緒に介護の未来をより良くしていきましょう!