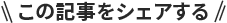SOMPO介護月間 「セミナー ~最新の認知症予防対策とは~」編

11月は、私たちSOMPOケアが「SOMPO介護月間」として、介護について一緒に考える特別な1ヶ月です。
今年は、「食と学び、そして“つながり”で創る介護の未来。」をテーマに、介護にまつわる “不” を見つめ直し、その解消につながる様々なイベントを各地で展開しています!
社内報WATCHでは、これまでにも以下のイベントを掲載しています。ぜひ、ご覧ください!
今回は、【学び】。専門家から直接聞ける貴重なセミナーを開催しました!テーマは、介護分野でも関心が高い「認知症」。
神戸大学大学院保健学科 リハビリテーション科学領域教授で、認知症予防推進センター長の古和久朋(こわ ひさとも)先生が「最新の認知症予防対策とは」と題して講演。セミナー後半には、脳と身体を一緒に動かす体験トレーニングも開催しました!
認知症を理解し、寄り添うために
前半は、古和先生による講演。「認知症のいま」と、私たちにできる予防の取り組みについて、最新の知見を交えながらお話しいただきました。 ■認知症は「特別な人の病気」ではない
■認知症は「特別な人の病気」ではない
・2025年には高齢者の4人に1人以上が認知症または予備群になると推計
・症状が出る20年ほど前から脳の変化が始まる
・神経細胞へのダメージは元に戻りにくいため「予防」の重要性が増している
認知症予防は、介護職員だけでなく、SOMPOグループで働くすべての従業員に関係するテーマであることが伝わる内容でした。
■ビジネスケアラーにならないために
・親世代の変化に気づくための“知識”
・少しでも早く相談につなぐ方法
・家族の将来を守るために、今できる備え
古和先生は、「本人だけでなく、家族全体の未来を守る視点が大切」と語られていました。
■多面的なアプローチで「脳の健康」を守る
当社と神戸大学が連携して取り組む「J-MINT PRIME Tamba研究」についても紹介がありました。
この研究は、兵庫県丹波市で18か月にわたり、運動・食事・認知トレーニング・生活習慣の見直しなど、複数の取り組みを組み合わせて行うものです。
・運動、食事、頭を使うトレーニング、生活習慣の見直しを組み合わせて取り組むこと
・歩きながら考える運動、タブレットを使った認知トレーニング、食事の振り返りなどを併用する
・こうした継続的な取り組みによって、認知機能の維持や改善が期待できる
これは、当社のSSAP(認知機能低下予防プログラム:SOMPOスマイル・エイジング・プログラム)にも確かにつながっています。
脳のトレーニングと有酸素運動を体験
後半は、当社で地域版SSAPを担当しているインストラクター・村上理香(むらかみ りか)さんが登場し、脳のトレーニングやストレッチなどの有酸素運動体験プログラムを実施しました。
 ■手指を使った脳トレーニング
■手指を使った脳トレーニング
・「1で押す/2で引く」などの数字と手指運動の切り替え
・「タイ」「タコ」など言葉に置き換えて連想しながら手指を動かす
■椅子を使ったストレッチ
・肩、胸、もも裏などのストレッチ
・股関節や足首まわりの柔軟運動
■立位の有酸素運動
・その場で足踏み
・サイドステップ+手拍子/おでこタッチ
・膝上げ+パンチ
 画面越しに一緒に取り組むグループ職員の姿も見られ、オンラインならではの一体感が広がる時間に。
画面越しに一緒に取り組むグループ職員の姿も見られ、オンラインならではの一体感が広がる時間に。
どの運動も、覚えながら切り替える動きが特徴で、自然と脳が刺激され、身体も温まる内容でした!
介護月間から、日々の実践へ
今回のセミナーを通じて、
・認知症を「誰にでも起こりうること」ととらえる視点
・家族の変化に気づき、早めの相談につなぐ行動
・脳と身体の両方を整える日々の取り組みの重要性
が、あらためて大切なポイントとして浮かび上がりました。
11月の介護月間を “イベント月” で終わらせるのではなく、 日々のケアを見つめ直すきっかけとして広げていきたいと思います!
このあともSOMPO介護月間の取組みは、順次お届けしていきます!
ぜひ、引き続きご覧ください!